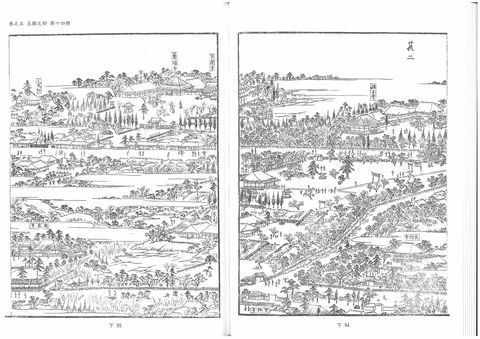Category
評価とコメント
 General 総合評価
General 総合評価
 Nature 自然環境(主に緑)とエコロジーへの配慮。
Nature 自然環境(主に緑)とエコロジーへの配慮。 坂は緩やかに湾曲しており、視覚的に美しい。道路脇の石垣にも風情が感じられる。
坂は緩やかに湾曲しており、視覚的に美しい。道路脇の石垣にも風情が感じられる。 Water 水への配慮
Water 水への配慮路線バスのルートでもあり、交通量が激しくあわただしい雰囲気である。
 Atmosphere 大気への配慮(風、香り、排気など)
Atmosphere 大気への配慮(風、香り、排気など)
 Flower 花への配慮
Flower 花への配慮 Culture 文化環境への配慮(街並、文化財、文芸関連)
Culture 文化環境への配慮(街並、文化財、文芸関連)
 建築物は情緒を感じさせるものがほとんどなく単調である。漱石鴎外などの文学に登場する。特に「三四郎」のベストシーンとして描写されている。
建築物は情緒を感じさせるものがほとんどなく単調である。漱石鴎外などの文学に登場する。特に「三四郎」のベストシーンとして描写されている。 Facility 設備、情報、サービス
Facility 設備、情報、サービス坂の景観を楽しむスポットはなく、無料休憩設備もない。
 Food 飲食
Food 飲食