

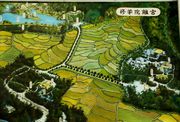
京都府京都市左京区 修学院離宮
Shugakuin Rikyu(Imperial Villa)、Sakyoku,Kyoto City,Kyoto
Feb.2,2018 中山辰夫
京都市左京区修学院薮添
17世紀中頃、後水尾上皇によって造営されたもので、上・中・下の3つの離宮からなり、借景の手法を採り入れた庭園として、わが国を代表するものとされる桂離宮とともに江戸初期を代表する山荘として並び称される
離宮は、明暦2年〜万治2年(1656-59)後水尾上皇が比叡山麓に造営した広大な山荘。
約54万5000㎡の敷地に上・中・下3つの離宮から構成され、いずれも数奇な趣向の茶亭等が閑雅にめぐらせた池の傍らに立つ 自然と建物の調和が絶妙とされる
現在の離宮は、隣雲亭・窮すい軒(きゅうすいけん)などのある上ノ茶屋と、寿月観のある下ノ茶屋、そして中ノ茶屋からなる
中ノ茶屋は第八皇女朱宮の山荘内に創立された林丘寺(りんきゅうじ)の跡地である
上ノ茶屋には大堰堤を築いて浴滝池と呼ばれる大池があるが、その規模は日本の庭園史上ほかに類例がない。舟遊びは伝統的な貴族の好尚で欠かせない
見学は案内に従って進む。約80分、3kmの距離を歩く
下御茶屋を目指す
総門〜御幸門〜寿月観〜東門、庭園は三方を取り巻く遣(やり)水・二つの池・中島・灯籠三基・枯山水の石組よりなる
表総門周辺
左右に磨き竹の袖塀をしつらえ、太い磨き丸太の門柱と磨き竹の門扉を取り付けた簡素な門で桂離宮とほぼ同じ形式、やや大きい。袖塀は腰から下に切石を組み、土が盛られており、桂離宮とはやや異なる
下御茶屋を目指す−説明
総門〜御幸門〜寿月観〜東門、庭園は三方を取り巻く遣(やり)水・二つの池・中島・灯籠三基・枯山水の石組よりなる
御幸門周辺
表総門から左手に曲がり緩やかな上り坂の砂利道をたどる
御幸門
入口である 石段の上にこけら葺の屋根を持つ簡素な門 両翼には袖塀を設け、大きな花菱形の透かし模様が目に付く 通用門から入る
苑池・遣水
遣水(小川)の滝口が一の間の東側にあり、ここから二の間、三の間の前を流れ池に流れ込む 小川の流し方は平安時代の寝殿造理の庭園に流した遣水の伝統を引継ぐ 中門(ちゅうもん)を通って苑池に入る 改修工事中で水の流れは見られなかった
苑池の周囲には楓やツツジが多く見られ、春や秋には寿月観の紅殻色の壁や水面に映る四季の情景が想像できる。改修工事中で水の流れは見られなかった
燈籠
袖形灯籠は別名、鰐口ともいわれ珍しい形で、切れ込みの上方にある蛭釘(ひるくぎ)に釣灯籠を下げて使う。朝鮮灯籠は反りを持たせた屋根に宝珠を乗せる
寿月観(じゅげつかん)−説明
前庭は一面に白川砂が敷かれた平地で、一の間と三の間につながる飛石が景観に変化をつくり出している
外観
石垣で土留めをした高みに建つ数奇屋風の建物である 現在の建物は文政年間(1818〜30)に旧規通りに復興されたもの
一の間(十五畳)・二の間(十二畳)・三の間(六畳)を逆L字形に配し、どの部屋からも庭園が楽しめる仕組み
明障子、濡縁を巡らす 屋根はこけら葺、一の間は寄棟造、三の間は入母屋造である 扁額は後水尾上皇の宸筆である
一の間−説明 (引用:修学院離宮(伝統文化保存協会)
一の間は十五畳敷で、三畳の栃框(とちがまち)の上段を設けて主座敷とする 凝ったつくりである
飾り棚
天袋に鶴、地袋に岩に蘭の絵 江戸後期の画家・原在中の筆 一間半の床を付す
杉板の花菱紋様の欄間と虎渓三笑の襖絵
二の間−説明
杉戸
三の間−説明
御茶屋山・東門〜御馬車道〜御茶屋山
下御茶屋の東門(裏門)は下御茶屋の出口 門を出ると視界が開ける 正面の山は御茶屋山、左は比叡山、右は東山の山々
斜面に向かってのびる松並木(御馬車道・道幅約2.5m)は中御茶屋に続く連絡路 一直線に延びる 御茶屋に向かう連絡路と分岐する
御水尾上皇は田圃の中の畦道を行き来されていた 明治天皇の行幸の際に植えられたアカマツの総数は約278本 しっかり維持されている
道の左右は棚田や田畑が連なり耕作が行われている 一部は国が買い入れて国有地となっており京都大学に貸与されていると聞く
中御茶屋表門・林丘寺跡旧表門・中門−説明
林丘寺
松並木道が終わり、表門が見えだすと左側に現れる(非公開) 所々からわずか見えるだけで全景は見れない 切妻造、本瓦葺の棟門
後水尾院(天皇)の皇女・光子内親王(朱宮)が後水尾上皇崩御の後、住まいの朱宮御所を寺院に改め、開山した寺院が林丘寺 皇女をもって住持とした
しかし江戸後期には無住が続き幕末には荒廃した 明治になって男僧が入り復興にあたり、楽只軒と客殿を宮内省に移譲して隣接地に書院・庫裏を移築して、再び尼寺となり現在に到る
表門
竹を詰張りした袖塀付きの門
中門
表門を入って幅の広い石段を上ると林丘寺の総表門であった切妻造、本瓦葺の棟門がみえる さらに進むと中門に至る ?葺の廂に襷掛けの二枚扉門
土蔵がみえる
中御茶屋
現在の離宮は内に庭園を抱いた上、中、下の三御茶屋で構成されているが、万治年間(1658〜1660)に創建の離宮は上、下の二御茶屋であった
いまの中御茶屋に隣接する門跡寺院「林丘寺」が明治17年、中御茶屋に当たる寺の一部と建物を宮内庁に寄付に寄付して整備され今日の姿になった
楽只軒と客殿および付帯の庭園からなる
楽只軒
楽只軒 (らくしけん)—説明
光子内親王の出家以前からの山荘風住宅。創建時の姿をとどめ平屋建て。
前庭と全景
前庭にある小さな苑池は創建当時からあったと伝え、客殿前からの遣水が流れ込む 石橋がアクセントになっている
外観
一の間—説明
貼付壁には「吉野の桜」 壁の絵が不鮮明なのは、寺の尼住持らが焚いた護摩のため
二の間−説明
壁の絵は狩野探信が描いた金地に龍田川の紅葉、色・柄の違う竹を三重にめぐらし七宝の竹葉をあしらった「楽只軒」の扁額 文字は後水尾法皇の筆跡
客殿−説明
入母屋造、栩葺(とちぶき)、高さの張った堂々たる宮殿建築 楽只軒よりより若干高い位置に建つ
この客殿は、東福門院がなくなられたあと、その女院御所にあった奥対面所を形見として、1689{天和2}年にここに移したもの
こけら葺屋根の平屋建て。一の間(十二畳)・二の間(十畳)・三の間(十畳)・内仏間(六畳)からなる。 飾り棚が有名
外観
客殿は宮廷建築でしかも女院の住まいであったため、その建物の外観にも内部にも雅かの面が目立つ 屋根は?葺きであるがの木は自重垂木 四周とも板張りの縁側が付
内仏間と網干の欄干
網干の欄干は数本の直線で構成される簡潔な木組の勾欄(手摺) 仏間の仏壇上部に欄間、戸袋には風景を描いた扇面が貼ってある
前庭
東隅に築いた滝口から遣水を流している。キリシタン灯籠や手水鉢が配置してある
一の間−説明
六畳の間、一間の床、床の間の正面奥と壁襖に、狩野探幽の子・探信が描いた吉野山の桜の絵が貼付されている。
飾棚
「霞棚」 峰々にたなびく霞のように見えると有名 桂棚(桂離宮)・醍醐棚(醍醐寺三宝院)とともに日本三大名棚と称される 公開は修学院離宮のみ
霞棚は大小5枚のケヤキ板製 棚板5枚の高さ,位置を少しずつ変化させ、正面から見ると流れたなびく霞を連想させる
床の間の貼布と腰張の金と群青の菱形つなぎ模様
金の砂子を散らして和歌とそれに因んだ絵の色紙を連ねる
地袋小襖や引手、三角棚に描かれている風景 羽子板形の引手
二の間−説明
寝所として利用されていた 一の間との境の襖絵は長谷寺の夜景が描かれ、筆者は狩野秀信
装飾意匠
客室杉戸の鯉 一の間(親子) 全体が網でおおわれている 夜毎に抜け出し池で遊ぶため金色の網で伏せたとの言い伝えがある
客殿杉戸・祇園祭山鉾・祇園祭船鉾及び釘隠し、金具
松並木道を通り上御茶屋へ向かう
大刈込
御馬車道の松並木越えの左前方に三段の高生垣と大刈込が見えだす この先多くの場所で見られる 景観上重要な構成要素である
上御茶屋-説明
松並木〜表門〜隣雲亭〜雄滝〜楓橋〜窮??亭〜土橋〜止々斎跡〜西浜上の白い苑路〜表門(帰路)
上御茶屋は谷川をせき止めて造った苑池を中心に造営されている。苑池周りに土堰堤を築き、石段を三段から四段に積んで土留めをしている。
借景に重点を置いた庭園美、展望美が一番美しいとされる
上御茶屋表門(御成門)
表門をくぐると急な石段が続き光景がかわる 大刈込の中を通る石段、しばらくすると一気に視界が開ける。
庭園中心部にある浴竜池の西岸堤上の白い一本道、道幅約1m、約200mを歩く 道右側は茶・ツバキ・ツツジ・アセビなど十種余が植えこまれた生垣 生垣は堤下まで続く 道左側は浴竜池が見えはじまる
隣雲亭(りんうんてい)
展望
工事中で残念でした。でも普段は見られないケースでした
京都タワーの展望台とほぼ同じ高さ(約149m)で、上茶屋の中で最も高い所にある。展望のために設けられた小亭である。
西側と南側に土廂(どびさし)をめぐらし、榑板縁(くれいた)を巡らす。 現在の建物は1824(文政7)年に旧来通りに再興された。
洗詩台と呼ばれる板間、外回りも間仕切りはすべて明障子 簡素な造り 山寺燈籠が立つ
一二三石(ひふみいし)
土廂の下は葛石で縁取りをした叩きの土間とし、そこに「一二三石」と呼ばれる赤と黒の小さい鴨川石を埋め込んである。
隣雲亭からの眺望
峰々
京都市街の一部や愛宕・西山の連峰が眺望できる
生垣の刈込と浴竜池方面、池中央の万松塢(ばんしょうう)が見渡せる
窮すい亭(きゅうすいてい)へ向かう
隣雲亭からは下り坂である〜滝見灯籠〜雄滝
滝見灯籠は面取りした四角い中台・竿の滝、石橋を渡ると右側の木立の中に高さ約6mの雄滝がある。工事中で水はストップ。小川風情である
万松塢(ばんしょうう)−説明
窮すい亭のある中島・万松塢・三保松の大きささまざまな三つの島が浮かび、苑池の景観に変化をつける
景観
もとの万松塢は岩も露わな小島 浴竜池の名もこの島の水面に浮かぶ竜に似た姿に由来する 万松塢と中島は千歳橋で結ばれている
千歳橋と千貫松
万松塢と中島を千歳橋が結ぶが当初は無かった。
切石積の二基の橋台上に、東側には瑞草をくわえた金銅の鳳凰をのせて鳳輦(ほうれん)になぞらえて宝形造、西側には寄棟造の東屋を設ける
さらに両屋の間に一枚石を渡して勾欄で繋ぎ、屋根をかけて廊橋としている 一風変わった佇まいである
中島にある窮すい亭へ行くには楓橋を渡る
楓橋
尾根を切り通した掘割りに架かる長い橋脚をもった小さな木の橋。周辺には楓の木が多くある。周辺には楓の木が多くある紅葉が待たれる
中島には石(千歳橋)と木(楓橋)と土(土橋)の三様の橋が架かっている
腰掛待合
万松塢の汀中ほどに見える紅殻色の腰壁を持つ、美しい四方吹き放しの切妻?葺の建物。明治天皇の行幸時に設けられた 舟遊び時の休憩用
窮すい亭(きゅうすいてい)−海抜149m余−説明
外観
中島の小高くなった所に建つ。後水尾上皇の創設当初より現存している唯一の建物
宝形造?葺の屋根に菊花紋のある大きい瓦の露盤と切籠形の宝珠頭を載せる
外回り
後水尾上皇宸筆の扁額 「窮」「すい」のそれぞれの文字を八角形で囲み、真中を水引で結んで対称な意匠 下には四角いくつぬぎ石が据えてある
上段の間・水屋−説明
十八畳と付属の水屋からなり、一隅に直角に折れて畳一枚高くした上段を設ける 上段西側一杯に低く一枚板を渡して御膝寄せとしている
母屋の南面と東面には深い土廂を出し、その下に回り縁を巡らす。宝形造りである
土橋
中島から北側の対岸に向かってかかる。木の橋であるが桁の上を土で覆っていることから「土橋」と呼ばれる。栗の欄干に小さな菊花紋の留金具が打ってある。
三保島−土橋の進行方向右側の景色
土橋の東側の山につながる島には松の木が多く繁り比叡山も顔を出す 比叡山を冨士山になぞらえ、三保の松原に因んで三保島と呼ばれた
西浜−左側の景色
豊に水をたたえた水面は大海の水平線を思わせ、その向こうには緑の芝生で限られた柔らかな汀の線、横一直線に伸びた大刈込の緑、その間を走る白砂の苑路−西浜の景観は自然と人工との織りなす見事なまでの調和により後水尾上皇の抱かれた理想の山荘の極致を示すとされる。
御舟屋付近
舟着き場付近
西浜汀の護岸工事
上御茶屋大狩込
土堰堤に三段の高生垣を仕立て、さらに上部を大刈込で覆っている 大刈込には常緑樹・落葉樹が混植され、四季の変化を色彩的に映し出すよう工夫されている 隣雲亭の大刈込とともに比類ない景観を生み出している
息抜き
帰路
参考資料≪パンフレット 修学院離宮(伝統文化保存協会)京都御所・利休の流れ ウイキパデイア 他≫
All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中