 General
General 
 Nature
Nature
 Water
Water Flower
Flower Culture
Culture
 Facility
Facility
 Food
Food
京都府 京都市/向日市/長岡京市/大山崎町 乙訓古墳群
Otokuni kofungun,kyoto City/Muko City/Nagaokakyo
City/Oyamazaki Town,Kyoto
Category |
Rating 凡例 |
Comment |
 General General |
 |
|
 Nature Nature |
 |
|
 Water Water |
||
 Flower Flower |
||
 Culture Culture |
 |
|
 Facility Facility |
|
|
 Food Food |
August 30,2025 大野木康夫
source movie
国指定史跡
指定の経緯
大正11(1922)年3月8日 天皇ノ杜古墳を史跡に指定
昭和56(1981)年10月13日 恵解山古墳を史跡に指定
平成27(2015)年3月10日 寺戸大塚古墳を史跡に指定
平成28(2016)年3月1日 上記3基に五塚原古墳、元稲荷古墳、南条古墳、物集女車塚古墳、井ノ内車塚古墳、井ノ内稲荷塚古墳、今里大塚古墳、鳥居前古墳の8基を加え、11基を乙訓古墳群として史跡に指定
平成30(2018)年2月13日 芝古墳、長法寺南原古墳を追加指定し、乙訓古墳群は13基となる
【芝古墳設置の京都市案内看板から引用】
京都市西京区山田以南の桂川右岸域(ここでは便宜的に「乙訓地域」と呼称)には、古墳時代を通して約400基もの古墳が造られました。これらの古墳のうち、前方後円墳や規模などの点で突出したものを「首長墓」と呼びますが、その数は全体の10分の1にも及びません。
乙訓地域は、一地域でこの首長墓が古墳時代を通して継続的に築造された稀な地域として知られています。これらの首長墓の様相は、ヤマト政権の政治的動向を反映していると考えられており、各古墳の調査・研究を通して乙訓地域の古墳は日本の古墳時代研究の礎を築いてきました。
これら乙訓地域の首長墓を現地保存し、そして後世に伝えていくために平成28年3月1日に11基の古墳が「国指定史跡 乙訓古墳群」として指定されました。また、平成30年2月13日には芝古墳等も追加指定されています。
乙訓地域の首長墓は、地理的に①樫原・山田グループ②向日グループ③長岡グループの3つに分けられます。芝古墳は長岡グループに含まれます。このうち、まず古墳の築造を始めるのは向日グループであり、それに樫原・山田グループが続きます。長岡グループでは、他のグループには遅れるものの古墳時代前期中葉に境野1号古墳や長法寺南原古墳が出現し、前期後葉には今里車塚古墳や鳥居前古墳が築かれます。古墳時代中期には、乙訓で最大規模を誇る恵解山古墳が築造されます。この恵解山古墳は約128mの前方後円墳で、前方部中央の副葬品埋納施設からは鉄製武器を中心に約700点もの遺物が出土していることから、古墳造営の背景にヤマト政権中枢との強い結びつきがうかがえます。しかし、この恵解山古墳以降はしばらく首長墓は造られず、空白期間が認められます。
その後、古墳時代中期末~後期前半になると芝古墳などの首長墓が再び造られますが、小規模でかつ数も増加しており、それ以前に比べて様子が異なります。芝古墳ではヤマト政権の中枢部でも採用され始めた「畿内型」の横穴式石室が確認できます。これは乙訓地域において最古級のものであり、その導入やヤマト政権との関係を考えるうえで重要です。
このような小規模な首長墓が造られるきっかけとして「弟国宮」の存在が注目されます。「日本書紀」によると「弟国宮」は518年に継体天皇によって遷都された宮殿です。芝古墳などの乙訓地域の小規模首長墓には、継体天皇に協力した乙訓の有力者が眠っているのかもしれません。
天皇の杜古墳
所在地:京都府京都市西京区御陵塚ノ越町
国道9号線天皇の杜古墳前信号のすぐ東側です。全体で引用した案内看板が「乙訓郡」ではなく「乙訓地域」となっているのは、樫原・山田グループの所在地が旧葛野郡だからと思われます。
墳丘に登ることができます。
【現地説明板から引用】
天皇の杜古墳は、京都市内でも極めて保存状態のよい前方後円墳で、古くから墳丘に生い茂る大樹が「天皇の杜」の名にふさわしい景観を見せています。
墳丘の形は前方部が広がらない、いわゆる「柄鏡式」の形態で、古墳時代も前期(4世紀代)に属しています。全長83メートルを測る市内では最大級の古墳で、その被葬者はこの時期に桂川右岸地帯を統括した有力豪族(首長)と推定されています。ここは、古来より交通の要衝であり、稲作の場である平野部を見わたすことができる大切な場所だったのです。
保存整備の一環として墳丘部と周濠部の部分的な発掘調査を実施しましたが、その結果、周濠部と理解されてきた平坦部には、周濠としての掘り込みはなく、兆域(墳墓の区域)として他と区別した部分であることがわかりました。墳丘は全体を2段築成で築造し、その平坦面には円筒埴輪が樹立していました。また、斜面には葺石が丁寧に葺かれていたことなども明らかになりました。
主体部(死者を安置した所)の調査は実施されていないため、埋葬施設や副葬品の内容までは明らかになっていませんが、桂川右岸では現存する前期の古墳が少ないだけに、かけがえのない古墳といえます。
なお、天皇の杜古墳の名称は、かつてこの古墳が文徳天皇(平安時代の天皇)の御陵であるとされてきたことに由来しています。















































芝古墳(芝1号墳)
所在地:京都府京都市西京区大原野石見町632-3
井ノ内車塚古墳のすぐ西北に位置しています。善峰道と丹波街道が交差する向井芝交差点の東50mほどから北に向かう枝道から入ったところにあります。近年、古墳公園として整備されました。
【現地案内板から引用】
芝古墳は、善峰川右岸の標高約50mの低位段丘上に立地します。芝1号墳とも呼ばれ、14基の古墳からなる芝古墳群のうちの1基で、その中で唯一の前方後円墳です。
平成25年~平成29年にかけて、京都市が保存を目的として調査を行いました。
芝古墳の墳丘下部は元々の地盤(地山)を削り出して形成しており、そのうrに後円部では約3m以上、前方部では約2.7m以上の土を盛って構築しています。
後円部中央には、南東方向に向かって開口する横穴式石室が存在します。奈良時代以降に石材が抜き取られていますが、部分的に石積みが残っていました。石室の北西隅と南西隅に設けられた石組み溝は特徴的です。
石室では副葬された高坏群や貯蔵器群(壺、甕、横瓶)がまとまって出土しました。また水銀朱の散布状況から、玄室西壁に沿って埋葬されていたと考えられます。この石室は通常時は外から見ることができない構造であり、使用の度に溝状の通路(墓道)を掘って石室内部に出入りしていたようです。この墓道をふさぐように4基の埴輪が据えられていました。この横穴式石室は現時点で乙訓地域で最古級のものであり貴重です。
芝古墳の近くには同時期の集落である上里遺跡が存在します、かた、付近では芝古墳の前段階の首長の墓が見つかっていないことから、被葬者はこの付近を本拠地とする新興勢力の長であったと考えられます。






























寺戸大塚古墳
所在地:京都府向日市寺戸町芝山
洛西竹林公園の南、西ノ岡竹林道の西側に位置しています。
【向日市埋蔵文化財センターホームページから引用】
全長約98m
後円部:直径約54m、高さ約10m、三段築成
前方部:幅約45m、二段築成
くびれ部:幅約35m
墳形は柄鏡形に近く、墳丘斜面には葺石が施され、墳裾、墳頂、各段の平坦面には埴輪が大量にならべられています。埋葬施設は後円部と前方部に竪穴式石槨が1基ずつ設けられています。後円部石槨は西山産の板石でつくられ、規模は全長6.45m、幅0.85m、高さ1.6mのです。舶載三角縁唐草文帯四神四獣鏡片、舶載三角縁仏獣鏡、素環頭大刀、斧、鎌、刀子、鑿、石釧、管玉、勾玉、埴製合子が出土しました。
前方部石槨は大阪府柏原市産出の安山岩の板石でつくられ、規模は全長5.3m、幅0.9m、高さ1.0mです。浮彫式獣帯鏡、倭製三角縁獣文帯三神三獣鏡、倭製方格規矩四神(わせいほうかくきくししん)鏡、琴柱形石製品、碧玉製紡錘車、管玉、直刀、短剣、鏃、斧、鎌、刀子が出土しています。
副葬品の組成と埴輪の特徴は、前期古墳の基準資料とされています。
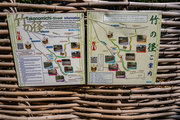

























五塚原古墳
所在地:所在地:京都府向日市寺戸町芝山3-1
向日町競輪場の北にあるため池「はり湖池」の西側山頂にあります。以前は墳丘に登れたのですが、現在は台風被害の影響で立ち入り禁止となっています。
【向日市埋蔵文化財センターホームページから引用】
全長約91m
後円部:直径約54m、高さ約9m、三段築成
前方部:長さ約41m、高さ約m4、二段築成
くびれ部:幅約15m、高さ約2m
奈良県桜井市箸墓古墳の墳丘規格の1/3相似形墳で最古型式の前方後円墳のひとつと考えられています。後円部と前方部の段築が連続せず、前方部の平坦面が墳頂と同じ高さまで大きくせりあがる「斜路状平坦面」は、この時期の古墳の特徴です。
墳丘の斜面には葺石、平坦面には礫敷が施され、全体が石で覆われた「石の山」のような外観であったと考えられます。後円部中央には川原石を用いた竪穴式石室がつくられ、墳頂には二重口縁壺が並べられました。元稲荷古墳や寺戸大塚古墳とともに墳丘規模が90m級と近似しており、墳丘の設計規格を同じくする可能性が高いとみられます。
















元稲荷古墳
所在地:京都府向日市向日町北山35
向日神社境内の北隣、勝山公園の中にあります。
【向日市埋蔵文化財センターホームページから引用】
全長約94m
後方部:長さ約50m、幅約49m、高さ約7m、三段築成
前方部:長さ約43m、幅約47m、高さ約4m、二段に築成
くびれ部:幅約24m
墳丘斜面に施された葺石は拳大の礫が多用されています。後方部中央に設けられた竪穴式石槨は南北方位で全長5.6m、北端幅1.3m、南端幅1.0m、高さ1.9mあります。合掌型に積み上げられた西山産のチャートの板石に、11枚の天井石が架けられています。内部は盗掘を受けていましたが、刀剣、槍、鏃、斧、鑿、刀子、鋤・鍬先などの副葬品が出土しています。前方部の墳頂中央には南北約2m、東西約4mの範囲に壺形土器をのせた特殊器台形埴輪が6~7個立てられていました。墳丘の各段に円筒埴輪の大量配列がはじまる直前の様相をもち、初期の竪穴式石槨の構造を備えるなど畿内の前期古墳の中でも最古の一群に属する古墳としてきわめて重要な位置を占めています。

























南条古墳
所在地:京都府向日市物集女町南条
第2向陽小学校の西隣、昌運寺墓地の中にあります。
【向日市埋蔵文化財センターホームページから引用】
直径約23.5m、高さ約3.5m
第2向陽小学校グランドおよび西側付近の扇状地に位置します。かつては7基の円墳がありましたが、現存するのは3号墳のみです。同時期の小型墳のほとんどが消滅したなか、墳丘が良好に残る点で貴重です。1983(昭和58)年、大阪大学文学部が測量調査を行い、その成果が『向日市史』に収載されています。また、平成19年(2007)には墳丘東裾で発掘調査が実施されています。墳丘には葺石が施され、埴輪がめぐらされていました。墳頂部中央に盗掘孔らしき凹み(径5.3m、深さ0.8m)が残ります。
















物集女車塚古墳
所在地:京都府向日市物集女町南条
交通量の多い府道67号に面しています。
【向日市埋蔵文化財センターホームページから引用】
全長:約46m
後円部:直径約24~32m、高さ9m、
前方部:長さ約18~23m、幅約39m、高さ約8m
くびれ部:幅約36m
墳丘は後円部、前方部とも二段築成。ごく一部に葺石が施され、埴輪が並べられていました。埋葬施設は6世紀初頭に成立する「畿内型」の横穴式石室で、玄室空間は床面が長方形で、天井は平坦、玄室入口に袖石を置き、羨道の幅は均一です。羨道に対して玄室が高く、袖石の上にのせる前壁は3段積みで、玄室左右の側壁は内傾させながら5段に積まれています。床には石組みの排水溝が設けられています。石室の構築石材の中には、中期古墳にみられる竜山石製の長持形石棺の部材が転用されています。物集女地域につくられた前代の有力者の墓を破壊してこの古墳はつくられたのかもしれません。副葬品は金銅装の冠や馬具、捩り環頭大刀、鉾、玉類などが確認されています。石室の構造と副葬品の内容から、継体大王の近くにつかえた新興豪族が葬られたと推測できます石室は毎年春季に一般公開されます。
































長法寺南原古墳
所在地:京都府長岡京市長法寺南原
長岡京市長法寺地区の低山の上に位置しています。私有地の竹やぶの中なので、立ち入ることはできません。
【長岡京市ホームページから引用】
長法寺南原古墳は4世紀後半に築造された、前方後方墳です。最初の発掘調査は昭和9年に実施され、後方部の竪穴式石槨から銅鏡、勾玉や管玉などの玉類、鉄製の武器や農具・工具、銅鏃、石臼や石杵など多彩な副葬品が出土しています。銅鏡は6面あり、その内の4面は三角縁神獣鏡です。長法寺南原古墳は、長岡京市では最も古い古墳であり、銅鏡など中央政権とのつながりを示す副葬品を複数有していることなどから、乙訓地域の権力者の盛衰を知るうえで重要な古墳といえます。












恵解山古墳
所在地:京都府長岡京市勝竜寺30
長岡京市南部、長岡第三中学の南に位置しており、恵解山古墳公園として整備されています。
【長岡京市ホームページから引用】
恵解山古墳は、古墳時代中期に築造された乙訓地域で最大の前方後円墳です。
桂川右岸の標高わずか16メートルの台地端につくられており、全長約128メートル、後円部の直径約78.6メートル、高さ10.4メートル、前方部の幅約
78.6メートル、高さ約7.6メートルと推定されています。周囲に幅約30メートルの周濠があり、周濠を含めた古墳の全長は約180メートルに及びます。古墳の表面には砂岩やチャートなどの葺石がふかれ、埴輪が並べられていました。死者を埋葬した施設は古くから墓地があるため明らかになっていませんが、後円部に竪穴式石室があったとみられます。昭和55年(1980)の発掘調査で、約700点にもおよぶ鉄製武器(直刀146点、鉄剣11点、短剣52点、短刀1点、ヤス状鉄製品5点、蕨手刀子10点、鉄鏃472点)を納めた副葬品埋納施設が見つかりました。このような多量の鉄製武器が出土した例は山城地方ではもちろんのこと全国的にも珍しいものです。こうしたことから、この古墳は5世紀前半頃に桂川以西の乙訓全域を支配した首長の墓と考えられます。
古墳は昭和56年(1981)に国指定史跡(指定面積19,496平方メートル)として、鉄製武器などの出土品は平成11年(1999)に京都府指定有形文化財としてそれぞれ指定されました。
そして、平成28年には、恵解山古墳をはじめとする首長墓群が「乙訓古墳群」として国の史跡に指定されることになりました。



































































井ノ内車塚古墳
所在地:京都府長岡京市井ノ内向井芝
京都府道10号善峰道向井芝交差点の東200mほどのところにある小さな古墳です。
【長岡京市ホームページから引用】
井ノ内車塚古墳は、6世紀前半に築造された前方後円墳です。この古墳の所在する地域は、古墳時代前期や中期に顕著な古墳が築造されなかった地域ですが、突如として古墳の築造が始まり、終末期(7世紀)まで継続的に造墓活動が進められます。また、井ノ内稲荷塚古墳、芝1号墳などの首長墓を頂点として、周囲に小規模な古墳や墳丘をもたない土壙墓などを伴って分布しており、大小様々な墳墓で構成される極めて階層差が明確な古墳群であると言えます。この地域の古墳は、新たに台頭してきた政治勢力の有力者が葬られていると考えられています。




















井ノ内稲荷塚古墳
所在地:京都府長岡京市井ノ内小西
京都西山高校第2グラウンド東南の竹やぶにあります。
【長岡京市ホームページから引用】
井ノ内稲荷塚古墳は、井ノ内車塚古墳に続いて築造された6世紀前半の前方後円墳です。後円部に横穴式石室、前方部に木棺直葬の埋葬施設がつくられており、横穴式石室は古式の畿内型横穴式石室が採用されています。副葬品は、鉄製武器類、金製刀装具、金銅張胡禄、金銅張馬具、装身具などが見つかっています。芝古墳、車塚古墳、稲荷塚古墳は、この時期の最上位に位置する墳形・規模を有するとともに、当時先端技術であった横穴式石室や金銅製品を導入するなど、重要な地位を占める首長の墓と考えられます。


























今里大塚古墳
所在地:京都府長岡京市天神5丁目20
長岡天満宮の北に広がる住宅地の中にあります。
【長岡京市ホームページから引用】
今里大塚古墳は、終末期(7世紀)に築造された最後の大型古墳です。埋葬施設は、巨石墳に分類される大型横穴式石室で、その規模は乙訓地域最大です。平面プランや石室壁面の構成は、石舞台古墳(奈良県明日香村)や山城最大の横穴式石室である蛇塚古墳(京都市右京区)と類似しており、畿内中枢部(大和政権)の直接的な影響下に成立した古墳といえます。




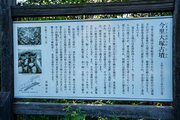















鳥居前古墳
所在地:京都府乙訓郡大山崎町円明寺鳥居前
天王山北麓、小倉神社の北に位置しています。
【鳥居前古墳パンフレット(2019 大山崎町教育委員会)から引用】
鳥居前古墳は、京都府乙訓郡大山崎町に所在します。標高90mの丘陵上に位置します。ここは、天王山から派生した独立丘陵の地形をしています。周辺から見上げると、古墳は、際だつ地形に立地していることがわかります。墳丘の眼下には、淀川の支流である小泉川の流域が展開しています。ここは、桂川・宇治川・木津川の合流点に近く、水陸交通の要地といえます。鳥居前古墳に先行して境野1号墳や土辺古墳が中・下流域に所在しています。また小泉川流域と犬川流域の境界には、恵解山古墳(長岡京市)が所在しており、鳥居前古墳に後続する存在として知られています。これら周辺の古墳は、鳥居前古墳の前後の時期にあ
たります。その存続期間は、古墳時代の前期後半から中期、およそ西暦350年頃から450年頃までの約100年間と考えられます。なお、鳥居前古墳は、西暦400年頃にあてられます。小泉川の、下流の地域では、大規模な集落遺跡が確認されています(下植野南遺跡)。これらのことから、小泉川流域(大山崎町周辺一帯)では、古墳造りと集落が一体となった社会の存在がうか
がえます。


















All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中