 General
General

 Nature
Nature
 Water
Water
 Flower
Flower
 Culture
Culture
 Facility
Facility Food
Food
奈良県奈良市 不退寺
Futaiji,Nara City,Nara
|
Category |
Rating
|
Comment
|
 General General
|
 |
|
 Nature Nature |
 |
|
 Water Water |
 |
|
 Flower Flower |
 |
|
 Culture Culture |
 |
|
 Facility Facility |
||
 Food Food |
奈良市法蓮東垣内町517 不退寺塔婆 重文 近世以前/寺院 鎌倉後期 鎌倉後期 桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、桟瓦葺(もと多宝塔下重) 古材7点 19080423
奈良市法蓮東垣内町517 不退寺南門 重文 近世以前/寺院 鎌倉後期 正和6(1317) 四脚門、切妻造、本瓦葺 旧懸魚1個 19040218
奈良市法蓮東垣内町517 不退寺本堂 重文 近世以前/寺院 室町前期 室町前期 桁行五間、梁間四間、一重、寄棟造、本瓦葺 19040218
August 16, 2025 野崎順次
source
movie
パンフレットと現地説明板
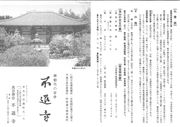



アプローチ






国重文 南大門












庫裏へ








消滅した平塚古墳出土といわれる舟型割竹くり抜き石棺
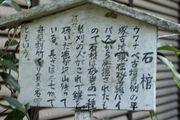






不退寺道角塔婆(室町時代中期、花崗岩、高さ 197Cm 幅・厚さ 30Cm)
以前は参道脇にあったが、本堂横に移された。
角塔婆は、四面を上・中・下段に分け梵字を刻む。上段は五輪塔四門の梵字、中段は金剛界四仏の種子、下段は
光明真言(南)、金胎蘇悉地三部・三帰依咒・胎蔵界大日如来真言(西)、大随求陀羅尼(北)、十三仏(東)を配している。
(河合哲雄「石仏と石塔」ウェブサイト)







国重文 本堂








国重文 多宝塔









境内の歌碑








木の幹に白い小さなキノコ群



静かな池








南大門から出て北の墓地に向かう。



不退寺墓地(ふたいじぼち)五輪塔(鎌倉代後期 花崗岩 高さ 215cm)
典型的な鎌倉時代後期の五輪塔で、「伝在原業平朝臣の墓」と呼ばれる。五輪塔は、切石の基壇上に複弁の反花座を置き、その上に据えられている。五輪塔は、各輪無地で、すっきりとした美しさを見せる。
(河合哲雄「石仏と石塔」ウェブサイト)















不退寺墓地背光五輪塔碑(桃山時代 文禄元年 1592年 高さ69cm 安山岩)
「キリーク」の下に「文禄元年辰、梅窓浄屋禅定門、十二月廿七日」
不退寺墓地背光五輪塔碑(室町末期、元亀四年 1573年 高さ73.5cm安山岩)
「五梵字」の下に「元亀二二辛未、春光禅尼、九月十四日」の刻銘
(河合哲雄「石仏と石塔」ウェブサイト)






その他、トンボ






Nov.2012 中山辰夫
宗派:真言律宗
本尊:聖観音
この地は平常復都を企てた平城太上天皇が萱の御所を営んだ所で、其の第1皇子が阿保親王を経て、親王の第5子在原業平に伝えられ、847(承和14)年、仁明天皇の勅を得て不退轉法輪寺としたという。
南都十五大寺の1つとして栄えたが、のち西大寺・興福寺の配下に入って、伽藍が復興された。
アプローチ
南門
国重要文化財
和様に大仏様を加味した新和様(折衷様)の四脚門 鎌倉時代後期の1317(正和6)年の建造
本堂
国重要文化財
寄棟造の新和様で、南北朝時代(14世紀)の建造と推定される。
本堂須弥壇上の厨子に安置される本尊の木造聖観音立像(国重文)は一木造の像、その両側に並ぶ木造五大明王像も国重文である。
塔婆
国重要文化財
本堂手前東側に立つ。一重・桟瓦葺・宝形造 鎌倉時代後期の新和様の建築方式で、本来は2層、檜皮葺の多宝塔だった。
古墳石棺
凝灰岩製である。どの古墳から出土したかは不明である。
庫裏
業平の歌碑
参考≪奈良県の歴史散歩 山川出版≫
A camera
B camera
Feb.2011 撮影:大野木康夫 source movie
所在地 奈良県奈良市法蓮東垣内町517
南門(重要文化財)
正和6(1317)年の建築
四脚門、切妻造、本瓦葺
石棺
ウワナベ古墳付近で発掘されたもの。
塔婆(重要文化財)
鎌倉後期の建築
桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、桟瓦葺(もと多宝塔下重)
本堂(重要文化財)
室町前期の建築
桁行五間、梁間四間、一重、寄棟造、本瓦葺
June 2009 撮影/文 野崎順次
奈良県奈良市法蓮町517
真言律宗
不退寺
(Futaiji Temple, Nara)
『大和國金龍山不退寺縁起』によると、第51代平城天皇は大同4年(809)に弟の嵯峨天皇に御譲位され、平城京の北東の地に萱葺きの御殿を造営、「萱の御所」と呼称された。その後、第1皇子阿保親王とその第5子在原業平朝臣が共に居住せられ、業平朝臣は承和12年(845)仁明天皇の詔を奉り、承和14年(847)平城天皇の旧居を精舎に改め、自ら聖観音像を刻まれ、父阿保親王の菩提を弔うと共に衆生済度の為に「法輪を転じて退かず」と発願し、金龍山不退転法輪寺と号して仁明天皇の勅願所となった。略して不退寺(業平寺)と呼ばれる。
建造物(*印は写真あり)
南門 (重文) 鎌倉時代末期*
本堂 (重文) 鎌倉時代*
多宝塔 (重文) 鎌倉中期*
仏像部
聖観世音菩薩立象 (重文)平安初期
五大明王像 (重文)藤原時代中期
阿保親王坐像 (県文)鎌倉時代
地蔵菩薩立象 弘仁時代
その他 石棺 5世紀*
All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中