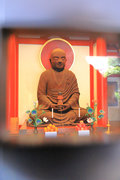JAPAN GEOGRAPHIC東京都中野区 宝仙寺
Hosenji,Nakanoku,Tokyo
|
Category
|
Rating
|
Comment
|
 General |
|
|
 Nature |
|
|
 Water Water |
|
|
 Flower Flower |
|
|
 Culture Culture |
|
|
 Facility Facility |
|
|
 Food Food |
|
|
May 26,2025 柚原君子
所在地;中野区中央2-33-3
平安時代(寛治年間1087~1094)、源義家が奥州征伐の帰途に護持していた不動明王像を杉並区阿佐ヶ谷の地に安置したことが始まりとされている。
現在地に移ったのは室町時代のこと。江戸初期には三重の塔が建立されたことで庶民にも親しまれるようになり、歴代将軍の鷹狩の際の休憩所でもあった。また、享保13年(1728)5月に江戸にやってきた牡象の骨があることでも有名。
中野区地域では非常に規模の大きいお寺で、宝仙学園も持つ。
境内には本堂や三重の塔のほか、多くの施設や史跡があり、明治時代以降は中野町役場が置かれていた時期もある。
仁王門を入ると左側に非常に立派な三重の塔がそびえている。
この塔は二代目でもともとの三重の塔は、1636(寛永13)年の江戸初期に建立され、廣重の浮世絵「江戸名勝図会」にも描かれている。
しかし1945(昭和20)年空襲で焼失。戦前の東京府の調査によれば焼失した塔は、当地の豪農である飯塚惣兵衛夫妻によって1636(寛永11年)に建立されたもので、方三間で屋根は檜皮葺(ひわだぶき)、高さは24m。塔内には飯塚夫妻の木像が安置され、裏面の墨書きにより夫妻が出資者で当時の住職が発願者であることが判明している。
この塔が建てられた江戸初期は、池上本門寺五重塔は、二代将軍徳川秀忠の乳母の正心院日幸尼の発願、上野寛永寺五重塔は幕府大老土井利勝の寄進、浅草寺五重塔は徳川3代将軍家光といずれも時の最高権力者により建てられたものであるが、豪族とは言え何故に一農民が建立できたのかは謎に包まれれている。
現在二代目の三重の塔は、奈良の法起寺の塔に範をとった飛鳥様式の木造建築で、大きさは焼失した塔とほぼ同じ約20m。
塔内には、大日如来を中心に宝幢、無量寿、開敷華王、天鼓雷音の胎蔵界五智如来の彩色された木像が安置されている。
ちなみに中野区一丁目にはかつて「中野区塔の山町」という地名が有り、現在でも塔山小学校というかつての三重の塔由来の地名が残されている。
三重の塔の手前にある「石臼塚」は近くを流れる神田川に江戸時代から水車が設けられてそば粉を挽いて、中野蕎麦と呼ばれて江戸市中の人の腹を満たしてきたが、機械化により不用になったため捨てられていた。それを人の食のために貢献した石臼を大切に供養すべきとして、宝仙寺が塚として供養している。塚の周囲は小さな池が有り、蓮の葉には蜻蛉の番が静かに止まっていた。












































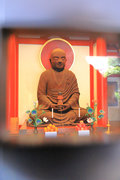










































All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中
 General
General 
 Nature
Nature
 Water
Water Flower
Flower Culture
Culture
 Facility
Facility Food
Food General
General 
 Nature
Nature
 Water
Water Flower
Flower Culture
Culture
 Facility
Facility Food
Food