 General
General 
 Nature
Nature
 Water
Water
 Flower
Flower Culture
Culture
 Facility
Facility Food
Food
京都府京都市下京区 東本願寺
Higashi Honganji ,Shimogyoku,Kyoto
Category |
Rating |
Comment |
 General General |
 |
|
 Nature Nature |
 |
|
 Water Water |
 |
|
 Flower Flower |
||
 Culture Culture |
 |
|
 Facility Facility |
||
 Food Food |
京都市下京区烏丸通七条上る常葉町754 真宗本廟東本願寺 御影堂 重文 近代/宗教 明治 明治28(1895) 桁行63.6m、梁間45.5m、二重、入母屋造、向拝三間、西面張出附属、すがる破風葺きおろし、南面及び北面下屋付、西面南北前室付、本瓦葺 "厨子1基 桁行一間、梁間二間、入母屋造、正面軒唐破風付、本瓦型板葺
造合廊下1棟 桁行13.9m、梁間5.5m、一重、唐破風造、本瓦葺、南北阿弥陀堂と御影堂に接続
二筋廊下1棟 桁行23.0m、梁間6.3m、一重二階建、両下造、本瓦葺、南北阿弥陀堂と御影堂に接続" 20190930
京都市下京区烏丸通七条上る常葉町754 真宗本廟東本願寺 阿弥陀堂 重文 近代/宗教 明治 明治28(1895) 桁行39.8m、梁間48.0m、一重、入母屋造、向拝三間、西面張出附属、すがる破風葺きおろし、南面及び北面下屋付、本瓦葺 宮殿1基 桁行一間、梁間一間、切妻造、正背面千鳥破風付、正側面向拝一間、唐破風造、本瓦型板葺 20190930
京都市下京区烏丸通七条上る常葉町754 真宗本廟東本願寺 御影堂門 重文 近代/宗教 明治 明治44(1911) 三間三戸二階二重門、入母屋造、左右繋塀及び山廊附属、本瓦葺 20190930
京都市下京区烏丸通七条上る常葉町754 真宗本廟東本願寺 阿弥陀堂門 重文 近代/宗教 明治 明治44(1911) 四脚門、切妻造、前後唐破風付、檜皮葺 20190930
京都市下京区烏丸通七条上る常葉町754 真宗本廟東本願寺 鐘楼 重文 近代/宗教 明治 明治27(1894) 桁行一間、梁間一間、一重、入母屋造、檜皮葺、腕木門附属 20190930
京都市下京区烏丸通七条上る常葉町754 真宗本廟東本願寺 手水屋形 重文 近代/宗教 明治 明治 桁行二間、梁間一間、一重、入母屋造、本瓦葺、石水盤及び井戸付 20190930
March 15 and 16, 2025 大野木康夫
source movie
3月15日
第59回京の冬の旅非公開文化財特別公開で42年ぶりに東本願寺の宮御殿と桜下亭(いずれも重要文化財)が公開されていたので参加しました。
3月15日は予約制(定員25名)の「僧侶が案内する特別拝観 東本願寺諸殿」に参加し、能舞台や白書院等も含めて見学しました。
見学は9時からだったので、8時頃からいろいろな文化財建造物を撮影していましたが、8時30分頃にカメラにSDカードを入れていなかったことに気が付き、近くのコンビニでSDカードを買ってツアーに参加しました。
案内図

阿弥陀堂、鐘楼、御影堂門、御影堂







説明の僧侶の引率でまずは阿弥陀堂へ






阿弥陀堂内部
ひととおり説明が終わったら自由拝観の時間があります。
時間が限られている(阿弥陀堂は3~4分)ので、金箔貼りの彫刻を中心に撮影しました。




















造合廊下を通って御影堂へ




御影堂内部
正面の大虹梁は15mあり、明治の再建当時に用材を探して、阿賀野川の川底に沈んでいた古代の木材を曳き上げて使ったということでした。
自由拝観は5分弱だったので、一部の彫刻の撮影に失敗しています。























宮御殿へ



ギャラリーから大寝殿の南側回廊を通って宮御殿へ向かいます。



宮御殿の外観はこの回廊からしか見ることができません。


大寝殿西側回廊から見た能舞台


宮御殿北側の廊下

宮御殿から見た南側の庭園
梅が咲いていました。







宮御殿(重要文化財)
明治34(1901)年の建築
建築面積243.70㎡、一重、入母屋造、東面北側便所及び北面東端廊下、西面北面便所付廊下附属、桟瓦葺
【月刊文化財から引用】
宮御殿は、近世来の殿舎の一つ「小寝殿」にあたり、大寝殿の南西に隣接して建つ。寺蔵文書によると、明治13年に明治天皇が下賜を約束した大宮御所の一宇を、明治34年4月、御真影遷座三百紀念法会に際して移築したと伝わる。建築面積243.70㎡、一重、入母屋造、桟瓦葺で、南面し、東面北側に便所、北面東端に廊下、西から北にかけて矩折れの廊下が附属する。平面は、表側に各24畳の主室と次の間を配し、背面側に突出して11畳と10畳の座敷を配す。北を除く三方に入側を廻らし、東と南には落縁と木階を設け、北側には縁側を廻す。表の座敷は、主室に繧繝縁の薄緣床、西楼棚の床脇、大振りな火灯窓の平書院を備え、貼付壁、格天井とし、裏の二室は11畳に繧繝縁の薄緣出床を構え、壁は漆喰塗で棹縁天井とする。室境の襖は人物描写や巧緻な筆致に特徴がある「子日遊図」をはじめ、「撰虫図」、「鷹狩図」等を配す。質実かつ格式高く、気品ある襖絵で飾られた上質の座敷からなる御殿である。
宮御殿回廊
南側回廊を西向に撮影したら、白い廊下(文化財指定なし)と宮御殿の廂との間に僅かですが黒書院の屋根が写っています。




表の主室





表の次の間と奥の主室

表の次の間「子日游図」







奥の主室「撰虫図」と欄間






奥の次の間「鷹狩図」





桜下亭は建物内撮影禁止なので周囲の百間廊下(附指定)を撮影



諸殿拝観へ

大寝殿回廊



大玄関


菊門


通路


通路の窓から見た能舞台橋掛



議事堂





表小書院








白書院












能舞台










大寝殿









桜下亭
左手奥の屋根は宮御殿、右手奥の屋根は黒書院











百間廊下





ツアーは約1時間10分でギャラリーに戻り、終了しました。
帰路の撮影
御影堂


御影堂門




菊門


玄関門



寺務所門


表小書院



議事堂


十三窓土蔵



内事門










内事日本館


3月16日1回目の訪問
15日にSDカード入れ忘れで取り残した分と、ツアーで撮り損ねた分を撮影するため再訪しました。
まず、御影堂・阿弥陀堂の室内撮影は法事や勤行の際はできないため、早朝、朝のお勤め(7時開始)前に再訪しました。
夜明け前の風景
御影堂門




御影堂



御影堂内の大虹梁、欄間彫刻、蟇股、宮殿、掛軸、壁画等を撮影しました。
御影堂の壁面の蟇股には彫刻は施されていません。



















































御影堂回廊からの撮影






造合廊下






二筋廊下

阿弥陀堂内の撮影
壁面の蟇股にも彫刻が施されていましたが、セルフタイマーが10秒しかないので撮り切れませんでした。





















































阿弥陀堂回廊からの撮影





鐘楼












御影堂門







御影堂
















水屋形


造合廊下

阿弥陀堂












阿弥陀堂と御影堂






阿弥陀堂門






御影堂










菊門

玄関門


築地塀




表小書院





議事堂


烏丸通東側から諸殿を撮影






3月16日2回目の訪問
10時過ぎから京の冬の旅の宮御殿・桜下亭特別公開(予約なし)に行きました。
予約制のツアーと異なるところは、(1)諸殿の見学がない、(2)宮御殿の奥の主室と次の間には入れない、(3)宮御殿東側の回廊には入れない、(4)桜下亭の竹の間の襖の前に柵が置いてあり近づけない、(5)桜下亭の松の間には入れない、(6)桜下亭の茶室には入れず、見ることもできない の6点でしたが、比較的すいていたので楽に撮影できた面もあります。
参拝者用駐車場から
内事門







内事日本館



十三窓土蔵



寺務所門

築地塀


玄関門

玄関門から見た大玄関・大寝殿の破風

菊門




諸堂遠景

東本願寺前マルシェ



御影堂門



御影堂

特別拝観
大寝殿南側回廊




宮御殿外観













大寝殿西側回廊



能舞台


白書院

桜下亭


百間廊下


宮御殿





奥の次の間
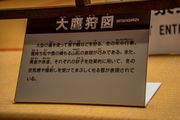













表の次の間から主室


表の次の間
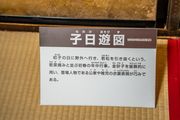









表の主室






























奥の主室


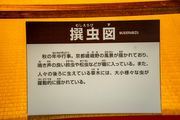













庭園

















黒書院の屋根の一部






宮御殿回廊








大寝殿


大寝殿、大玄関


Oct.21,2024 柚原君子
阿弥陀堂
御影堂
御影堂門
October 7,2023 大野木康夫
令和5年9月25日付で、真宗本廟東本願寺の建造物14棟が重要文化財に追加指定されました。
また、それとは別に、真宗本廟東本願寺内事3棟も重要文化財に指定されました。
既指定の建造物
阿弥陀堂門






御影堂門

















御影堂


















阿弥陀堂












造合廊下(附指定)



手水屋形


鐘楼(修理中)

新指定の建造物(附指定を含む)
築地塀 阿弥陀堂門南方(附指定)
明治12(1879)年頃の建造
折曲り延長197.4m、通用門一箇所付、本瓦葺












築地塀 御影堂門南方(附指定)
明治12(1879)年頃の建造
折曲り延長60.5m、戸口一箇所付、本瓦葺


築地塀 御影堂門北方(附指定)
明治12(1879)年頃の建造
折曲り延長110.6m、通用門及び戸口一箇所付、本瓦葺







菊門
明治44(1911)年の建築
四脚門、切妻造、前後唐破風付、両脇袖塀付属、檜皮葺












































築地塀 菊門北方(附指定)
明治12(1879)年頃の建造
折曲り延長45.7m、本瓦葺




玄関門
明治44(1911)年の建築
三間一戸薬医門、本瓦葺、両脇袖塀付属、潜戸付
















築地塀 玄関門北方(附指定)
明治12(1879)年頃の建造
折曲り延長128.0m、戸口一箇所付、本瓦葺



















寺務所門
明治44(1911)年の建築
一間薬医門、両脇袖塀付属、潜戸付、本瓦葺



















築地塀 寺務所門西方(附指定)
明治12(1879)年頃の建造
延長12.3m、本瓦葺




十三窓土蔵
明治15(1882)年の建築
土蔵造、建築面積317.54㎡、二階建、寄棟造、本瓦葺、南面及び東面庇付、棧瓦葺































内事門
明治15(1882)年の建築
長屋門、建築面積317.54㎡、二階建、入母屋造、唐破風造両出番所附属、本瓦葺




























大玄関及び大寝殿
慶応3(1867)年の建築
大玄関及び大寝殿よりなる
大玄関 建築面積450.62㎡、一重、入母屋造、棧瓦葺
大寝殿 建築面積805.06㎡、一重、入母屋造、棧瓦葺












議事堂
昭和10(1935)年の建築
建築面積512.01㎡、一重、入母屋造、棧瓦葺








表小書院
昭和10(1935)年の建築
建築面積196.30㎡、一重、寄棟造、東面北端下屋付廊下附属、東面南端及び南面廊下附属、棧瓦葺

真宗本廟東本願寺内事
日本館
大正12(1923)年の建築
木造、建築面積793.64㎡、棧瓦葺、東・南渡廊下、小書院附属











洋館
大正12(1923)年の建築
鉄筋コンクリート造、建築面積1,316.23㎡、二階建一部三階建、桟瓦葺、南・北渡廊下附属






Feb.5,2023 野崎順次
source movie
第57回「京の冬の旅」では、大河ドラマにちなみ、徳川家康や同時代を生きた戦国武将ゆかりの寺院、令和5年(2023)の「親鸞聖人御誕生850年」「立教開宗800年」慶讃法要と、「弘法大師御誕生1250年」「真言宗立教開宗1200年」にちなんで、各本山寺院の仏教美術やその文化にスポットをあて、普段は見学できない庭園、仏像、襖絵、建築などの文化財が期間限定で特別公開されます。
~近代和風建築を代表する「お東さん」の通常非公開の文化財~
真宗大谷派の本山で、正式名称は「真宗本廟」。慶長7年(1602)、徳川家康から土地の寄進を受けて建立された。儀式等に使用される大寝殿の障壁画「風竹野雀図」「歓喜図」「古柳眠鷺図」は、京都画壇を代表する日本画家・竹内栖鳳が手がけたもの。来賓の接待などを行う白書院は帳台構や違棚を設けた書院造で、独創的な彫刻と藤や牡丹を中心とした障壁画が美しい。
(JRおでかけネット 京の冬の旅サイト)
パンフレットと現地説明板

















境内に入り参拝接待所の奥へ



国登文 大寝殿





























渡り廊下を進む。








表小書院



庭園





能舞台













白書院






























その他






慶長撞鐘














Feburuary 25,2022 大野木康夫
source movie
御影堂門(重要文化財)










御影堂(重要文化財)



御影堂門特別公開(京の冬の旅)

階段下から撮影
階段途中はおそらく安全上の理由で撮影禁止
楼上室内も撮影禁止


回廊東側










回廊北側






回廊西側





回廊南側



楼上からの伽藍の眺め




















帰路


January 25,2020 大野木康夫 source movie
真宗本廟東本願寺
真宗本廟東本願寺は,京都市街に壮大な伽藍を構える本山寺院である。
現在の伽藍は元治元年(1864)の焼失後,幕末から昭和にかけて順次再興された。
御影堂は明治28年の建立で,17世紀中葉以来の規模と形式を継承しており,我が国最大の平面規模をもつ雄壮な伝統木造建築である。
御影堂と並立して両堂形式を構成する阿弥陀堂は,格式高く荘厳な内部空間を備えている。
両堂の前には烏丸通に面してそれぞれ門を開き,御影堂門は我が国最大級の二重門である。
比類ない規模と高い格式を備えた近代の木造寺院建築群として高い価値を有する。
(文化庁広報資料より)
将軍塚展望台からの遠望


御影堂門(重要文化財)
明治44(1911)年の建築
三間三戸二階二重門、入母屋造、左右繋塀及び山廊附属、本瓦葺

































手水屋形(重要文化財)
明治28(1895)年の建築
桁行二間、梁間一間、一重、入母屋造、本瓦葺、石水盤及び井戸付











鐘楼(重要文化財)
明治27(1894)年の建築
桁行一間、梁間一間、一重、入母屋造、檜皮葺、腕木門付属







阿弥陀堂門(重要文化財)
明治44(1911)年の建築
四脚門、切妻造、前後唐破風付、檜皮葺





御影堂(重要文化財)
明治28(1895)年の建築
桁行63.6m、梁間45.5m、二重、入母屋造、向拝三間、西面張出附属、すがる破風付葺きおろし、南面及び北面下屋付、西面南北前室付、本瓦葺























造合廊下(御影堂の附指定)





二筋廊下(御影堂の附指定)


阿弥陀堂(重要文化財)
明治28(1895)年の建築
桁行39.8m、梁間48.0m、一重、入母屋造、向拝三間、西面張出附属、すがる破風付葺きおろし、南面及び北面下屋付、本瓦葺





















Oct.2011 中山辰夫
真宗本廟東本願寺
京都市下京区烏丸通七条上ル
真宗大谷派本山
JR京都駅から烏丸通りを北上すること5分。左手に豪壮な伽藍群が見える。
これが“お東さん”と呼ばれ、京都市民から親しまれている東本願寺。正式には真宗本廟という。
本願寺十二代教如(きょうにょ)上人が慶長7年(1602)に徳川家康の支援を得て開いたお寺である。
慶長7年(1602)に境内をこの地と定めて以来、元治元年(1864)に起こった“蛤御門の変”による大火で焼失にあい、明治13年(1880)
から15年の歳月をかけて、明治28年(1895)に再建された。
東本願寺は、現在まで4度の焼失と再建の繰り返しで、“火出し本願寺”と囁かれたこともある。また再建毎に社殿が大きくなった。
東本願寺では、宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌特別記念事業として、真宗本廟両堂等の修復工事が決定された。
百十余年を経過した伽藍は修復の時期に来ており、今回の記念修復事業となった。総工事費は200億円を越えるようである。
平成16年(2004)3月から着手された御影堂(ごえいどう)の工事は完了し一般公開中である。阿弥陀堂は工事継続中、
御影堂門は今秋着手され、すべての完了は平成25年(2015)予定となっている。
修復工事着手前の伽藍
本願寺の周囲はお堀で囲まれている。
大通りに面する4門−阿弥陀堂門・ 御影堂門・ 菊の門・ 玄関門−にはそれぞれ風格がある。
東本願寺境内
現在の本願寺は、約28,000坪の広さをもち、大きく両堂・白州部分と諸殿部分に分かれる。
両堂・白州部分は法要・諸行事の中心であり、多くの門徒が参詣できるよう広くとられている。諸殿も明治以降に順次再建された。
明治を代表する重厚かつ勇壮な名建築は、全国からかけつけた延べ1000万人に及ぶ信仰心で築き上げられたとされ、江戸時代
以来の建築構成・様式を踏襲して建てられている。社殿の殆どが国登録文化財指定である。
堀を渡り、門をくぐって広い境内に入ると目の前は白砂の広場となる。その先に真新しい・・巨大な御影堂が目に飛び込む。
明治28年(1895)に再建されたもので、間口76m、奥行58m、高さ38m、広さ畳927畳分という世界最大級の木造建築である。
御影堂
その南側に並んで建つ阿弥陀堂(本堂)は、ひとまわり小さいが、白色の大きな“覆い 素屋根”にスッポリと納まっている。
阿弥陀堂
その他の諸堂も両堂と同じく明治時代以降に順次再建されたもので、まだ新しいものばかりである。今も門徒の接待等に使用される。
今回の修復を終えると、今後150年近く経た後に次の修復時期を迎えることになる。それを思うと重要な工事である。
世界最大級の木造建築の建造は大変な事業で、明治に15年の歳月を掛けて行われた。その内容は添付資料を参照されたい。
百数十年前の再建時の逸話として、真宗門徒に語り継がれているひとつに“毛綱(けづな)がある。
御影堂建築には巨材を用いたため普通の運搬用の綱では切れてしまう。
そのため女性門徒たちが髪を切って、それをロープ状に編んだ。この強靭な"毛綱“がなければ、根本道場の再建は出来なかった。
その実物の一部が御影堂と阿弥陀堂を結ぶ廊下に展示されている。大橇(そり)とともに門徒の再建への尽力を伝えている。
尾神嶽師殉難
平成の大修復においては“環境問題”が大きなテーマとなった。御影堂だけでも破損した瓦が12万枚あったようだ。この再利用を
含めた種々の環境対策については添付の資料を参照されたい。
すべての修復事業が完了する平成27年(2015)が待たれる東本願寺である。
法宝物について
以下は、特別拝観時に東本願寺より配布されたパンフレットよりの引用である。
東本願寺(真宗本廟)の歴史
両堂再建の歴史
親鸞聖人のご生涯
しんらんさまめぐり 京都編
しんらんさまめぐり 関東編(その一)
しんらんさまめぐり 関東編(その二)
しんらんさまめぐり 関東編(その三)
大谷祖廟
唐獅子牡丹図 望月玉泉筆 (御影堂内陣)
■■■ 阿弥陀堂・修復現場
真宗本廟東本願寺阿弥陀堂
国登録文化財
本尊:阿弥陀如来
阿弥陀堂修復工事前
素屋根(修復作業中の風雨を防ぎ、建物が保護された状態で作業が行える環境を作り出すもの)に覆われた状態
素屋根は、御影堂の修復が終わり阿弥陀堂に移された。
高さ51m×幅79m×71mと御影堂の屋根よりも高い。
阿弥陀堂の概要
阿弥陀堂は御本尊・阿弥陀如来を安置する本堂である。焼失と再建の歴史を経る中で、徐々に規模が拡大され
現在では創建当初の敷地面積の約2倍の平面積となっている。
工事中の堂内
修復工事中の阿弥陀堂の参拝路は階段になっている。本堂の周りは鉄柱が取囲むが、参拝には支障のないよう配慮されている。
本堂の組物
建築:明治28(1895)
構造:木造平屋建、瓦葺、建築面積1987㎡
基準:他の規範となるもの
外陣の豪壮な組み物 百数十年経過を感じさせない。
解説:御影堂南に並んで東面して建つ。
単層,入母屋造,本瓦葺,組物は側柱上が四手先,入側柱上は三手先とし,平面は真宗本堂の典型を持つ。
御影堂に比して格段に複雑な組物を備え内陣回りは全面金箔押しで荘厳を極める。御影堂とともに寺観構成上欠かせない建物。
堂内
「仏説阿弥陀経」の世界を表現する内陣は、金色で荘厳されている。
内陣最南部の襖を飾る、岸竹堂作・[桜孔雀図]。精緻な筆致つがいの孔雀が描かれている。
修復中の阿弥陀堂大屋根の見学
特別拝観を許された工事現場に上り、修復を待つ大屋根を目の前にした。素屋根の中に納まって修復を待っている。
地上8mの見物場まではエレベーターか階段を利用する
修復を待つ阿弥陀堂の屋根瓦、組物
目の前の大屋根を手に取るように見ることができる。
明治の再建から100年以上が経過しており、欠け、脱落、凍害などが確認されている。使用される瓦は焼く11万枚である。
雨漏り、白アリ被害、木部の腐食、などの様子が見える。
錺金物の欠損、ススや由縁による汚れ、瓦破損、などが起こっている。
工事前の調査は徹底を期す
工事現場構え
見学場所から見る
東山連山も見える。修復が完了した御影堂の大屋根も手に取るように見えた。
展示場
素屋根の一郭に御影堂工事実施内容を中心とした展示コーナーが設けられており、説明が並んでいる。
阿弥陀堂修復工事概要
■■■ 阿弥陀堂門・築地塀
真宗本廟東本願寺阿弥陀堂門南側築地塀
国登録文化財
建築:明治28年以前(1911)
構造:土塀、瓦葺、折廻り延長96m
理由:国土の歴史的景観に寄与しているもの
解説:阿弥陀堂門の南方に折曲がりに約100m続く土塀で,外堀に面する外側は切石垣基礎を築きその上に建つ。
柱形をあらわして出桁で垂木を受け本瓦葺屋根を架け,柱間漆喰壁面には5筋の目地を付けた本格的な築地塀。
中間の折曲がり部の南方は大正に延長された。
真宗本廟東本願寺阿弥陀堂門
国登録文化財
建築:明治44(1911)
構造:木造四脚門、切妻造、唐破風付、檜皮葺、建築面積31㎡
菊の門や玄関門と同形式、同時期の落成である。かつて[唐門]と呼ばれていた。
理由:造形の規範となっているもの
【表門側】
【境内側】
解説:御影堂門と同じく宗祖650年遠忌に際して建設。
四脚門形式,切妻造,檜皮葺で,前後に唐破風を付ける。
四脚門としては最大級の規模であるとともに頭貫木鼻や欄間に精緻な彫刻を用いて飾る。
御影堂門南に並んで建ち,壮大な伽藍の正面構成上欠かせない建物。
■■■ 白書院・能舞台・黒書院
白書院
大寝殿の西北に位置し、三方が庭園に囲まれている。門首と門徒の対面場に使用される。
明治44年(1911)の親鸞聖人六百五十回遠忌の際に、大阪の戸田猪七氏の寄贈により再建された。
建物の北側脇には控え間と上段の間が設けられている。
上段の間は帳台構・違棚などを設けた正式の書院造である。
白書院の装飾には京都府技師・亀岡末吉が顧問として参加している。
正式の対面所であるが、上段を除き内部の装飾は控え気味である。
中央・上段の間は格天井、控間は小組格天井、一の間は折上小組天井となっている。
“ふじ”が描かれている。親鸞聖人が藤原氏の末裔であること、経済面での支援者であった鴻池氏との関係からフジが採用された。
能舞台
明治13年(1880)の両堂釿始式(ちょうなはじめしき)の際に、白州の仮設用として組みたてられたもの。
現在の位置には昭和12年(1937)に常設として設置された。
現在の能舞台は白書院を観覧席として建てられている。現在でも御遠忌をはじめ大法要の際に能が舞われる。
佇まい 右側の建物は大寝殿・宮御殿
鏡板には、明治期京都画壇の重鎮・幸野楳嶺(こうのばいれい)が雄大な松を描いている。
黒書院(くろしょいん)
宮御殿を挟んで白書院の西奥に位置する。
かつては門首の私的な応接施設として、明治44年(1911)に建てられた。
内部は亀岡末吉(京都府技師)が日本古建築の細部意匠を参考にして創作した図様や、加藤英舟(えいしゅう)等の障壁画で飾られている。
黒書院・白書院や御影堂などの諸門は、いずれも同年の親鸞聖人六百五十回御遠忌に間に合うように再建されたものである。
黒書院の庭は、御影堂の大屋根を借景とした雄大な眺めである。
西座敷一の間は、幸野楳嶺・竹内楢鳳に師事した画家・加藤英舟の障壁画で飾られている。
東座敷、三之間から一之間を見る。
東座敷一之間。床や長押上壁には、古建築に造詣の深い亀岡技師が、正倉院御物の文様を参考に考案した図様が散りばめられている。
参考資料≪真宗本廟東本願寺(東本願寺出版部)より引用≫
■■■ 菊の門・北南築地塀
真宗本廟東本願寺菊の門 北・南側築地塀
国登録文化財
建築:明治44(1911)
構造:木造四脚門、檜皮葺、建築面積31㎡
理由:造形の規範となっているもの
南側築地塀
北側築地塀
解説:御影堂門と同じく宗祖650年遠忌に際して建設。
四脚門形式,切妻造,檜皮葺で,前後に唐破風を付ける。
四脚門としては最大級の規模であるとともに頭貫木鼻や欄間に精緻な彫刻を用いて飾る。
御影堂門南に並んで建ち,壮大な伽藍の正面構成上欠かせない建物。
真宗本廟東本願寺菊の門
国登録文化財
建築:明治44年(1911)
構造:木造四脚門、切妻造、唐破風付、檜皮葺、建築面積33㎡、左右袖塀付 阿弥陀堂門、玄関門と同形式、同時期の落成である。
基準:造形の規範となっているもの
[表側・大通り側]
[裏側・境内側]
解説:御影堂門の北方に大寝殿への表門として宗祖650年遠忌事業で建設された。
四脚門,切妻造,檜皮葺で,前後に軒唐破風を付し,木部は総漆塗とする。
設計は亀岡末吉で,全体は伝統的な四脚門の形式を踏襲しつつ,彫刻や木鼻絵様には近代的感覚が充溢している。
参考資料≪国データーベース、他≫
■■■ 真宗本廟東本願寺宮御殿(みやごてん)
宮御殿は、北海道開拓などの政府の方針に積極的に加担したとして明治政府から贈られた。政府は、両本願寺に贈与する内容に窮したようだ。
慶応3年(1867)、京都御所内の旧大宮御所にあった御殿を明治13年(1880)に渉成園(しょうせいえん)の大玄関とともに贈られたものである。
部材のまま保管されていたが、明治34年(1901)の[御真影遷座三百年記念法会]に合わせて御影堂北側の現在地に建てられた。
各室とも畳の縁は紅色で統一され、かつて御所にあった建物であることを彷彿させる。
室内は瀟洒な「四季行事絵図(作者不明)」として、春の「子日遊図 ねのひあそび」、秋の「撰虫図(むしえらび)」、冬の「大鷹狩図」の
襖絵で飾られている。
また、宮御殿南側は、四季の移ろいが美しい庭園となっており、築山の南側が約5mの防火壁(石垣)として類焼を防ぐように工夫されて
居ることから、先達(せんだつ)の本廟護持の想いが感じられる場所である。
■■■ 玄関門と築地塀
真宗本廟東本願寺玄関門南側・北側築地塀
国登録文化財
建築:明治28年以前(1895)
構造:土塀、瓦葺、折廻り延長88m
理由:国土の歴史的景観に寄与しているもの
南側
北側
解説:玄関門の北,寺域北辺を限る乾町通りに至るまでの土塀。
南端部で短く斜めに折れ,寺域の鬼門となる北端部は折曲がりに隅を欠き取るように配され,伽藍正面,烏丸通り側北端部の景観を整える。
南端部折曲がり部より北は大正に寺域が拡張されてから延長された。
真宗本廟東本願寺玄関門
国重要文化財
建築:明治44(1911)
構造:木造薬医門、切妻造、唐破風付、瓦葺、建築面積26㎡、左右袖塀付 阿弥陀堂門・菊の門と同形式、同時期の落成である。
棟梁は御影堂門を担当した市田重郎兵衛の息子、辰蔵。彼は白書院の棟梁でもあった。
理由:造形の規範となっているもの
表門側[大通側]
裏門側[境内側]
解説:菊の門のすぐ北に並んで建つ。
薬医門形式,切妻造,本瓦葺で,桁行を3間に分け,中央間を戸口とし両脇に板壁の脇間をとる。
桁行約8.6m,棟高約10mの大型の薬医門で,装飾は少ないが派手な絵様の肘木や頭貫木鼻により,華やかで堂々とした構えを造る。
■■■ 御影堂
真宗本廟東本願寺御影堂
国登録文化財
平成16年(2004)から約5年の歳月を掛けて、平成20年(2008)修復工事を終えた。
110余年ぶりに往時の輝きを取り戻した御影堂である。
御影堂は、宗祖親鸞聖人の御真影を安置する本廟内で最も重要な建物で、真宗大谷派の御崇敬(ごそうきょう)の中心である。
境内のほぼ中央に東面して建ち、南北76m(42間)、東西58m(32間)、高さ38m(21間)の規模を持つ世界最大の木造建築物である。
御真影の左右には歴代門首の御影や十字・九字の名号が掛けられている。
明治12年(1879)から16年の歳月を掛けて、明治28年(1895)に落成した。
大屋根を葺く約17万5000枚といわれる瓦は、三河(愛知県)門徒の手によって製作・寄進されたものである。
概要
1878年の再建の発示から16年、延130万人の人びとが再建工事に携わった。
建築:明治28年(1895)
構造:木造平屋建、瓦葺、建築面積4039㎡
基準:造形の規範となっているもの
解説:元治元年火災後の再建。
二重仏堂,入母屋造,本瓦葺,組物は上層三手先,下層は出組及び二手先とする。
間口及び面積においてわが国最大の仏堂で,伝統様式・技法による木造建築の集大成を示す。
棟梁伊藤平左エ門により明治13年釿始以来16年をかけて完成。
御影堂の規模は壮大であるが、優美な屋根の稜線が威圧感を感じさせない。
庇部は豪壮な組み物で構成されている
木階部廻り
御影堂を支える巨大な丸柱は90本。主な用材については、献木した国や人の名前が克明に記録されている。
外陣に敷かれた畳は700余畳。内陣を合わせると927畳に及ぶ。
内陣に安置される御真影≪宗祖親鸞聖人≫御影堂の内陣は阿弥陀堂とは趣を異にし、道場(住宅)風の比較的質素な意匠である。
【御影堂御修復のあゆみ】 特別拝観時に東本願寺より配布されたパンフレットより引用
【御影堂の御修復について】 内容が重複するところがあります。 配布パンフレットより引用
参考資料≪東本願寺発行パンフレット、他
■■■ 御影堂門・塀・堂
真宗本廟東本願寺御影堂門 南・北側築地門塀
国登録文化財
建築:明治28年以前(1895)
構造:土塀、瓦葺、折周り延長55m
基準:歴史的景観に寄与するもの
解説:(南側)阿弥陀堂門の北,御影堂門との間に折曲がりに続く土塀で,御影堂門の脇には戸口1所を開く。
他と同様に内外とも柱形を見せ,柱間漆喰壁に5筋の目地を切った本格的な築地塀で,両門の前で矩ね折れとなり,
正面両端に小さな妻面を見せ変化に富んだ外観を造る。
[北側]
解説:御影堂門の北方,菊の門との間に折曲がりに続く土塀。南寄りに参拝所への通用門を設け,
御影堂門側にも戸口1所を開く。
他と同様の本格的な築地塀で,烏丸通りに面して寺域を限る延長さ100mを越えて一直線に連なる姿は,
壮大な伽藍構成上欠かせない存在。
[南側]
解説:阿弥陀堂門の北,御影堂門との間に折曲がりに続く土塀で,御影堂門の脇には戸口1所を開く。
他と同様に内外とも柱形を見せ,柱間漆喰壁に5筋の目地を切った本格的な築地塀で,両門の前で矩ね折れとなり,
正面両端に小さな妻面を見せ変化に富んだ外観を造る。
真宗本廟東本願寺御影堂門
国登録文化財
高さ約28mの重層造り、左右に山廊(さんろう)を付す。
建築:明治40年(1907)起工、明治44年(1911)落成。
構造:木造二重門、瓦葺、建築面積328㎡、左右山廊付
基準:造形の規範となっているもの
大通り側全貌
外観
境内側全貌
外観
屋根の流線
組み物
装飾
解説:明治40年宗祖650年遠忌事業として再建。
三間三戸二重門,入母屋造,本瓦葺で,下層は二手先,二軒繁垂木,上層は三手先,二軒扇垂木とし,左右に山廊を付す。
大型で立ちが高く彫刻や細部の意匠にも優れ,寺域への正門として伽藍正面の構えを整えている。
獅子 総本山としての荘厳な雰囲気を醸し出す役目を果たしているようだ。
楼上には[真宗本廟]の額が掲げられ、浄土真宗の根本経典『仏説無量寿経(ぶっせつむりょうじゅきょう』の会座(えざ)
を表わす、釈迦如来・阿難尊者(あなんそんじゃ)・弥勒菩薩(みろくぼさつ)の三尊像が安置されている。
今年度より修復工事が着手され、2015年完了予定となっている。
御影門楼上の特別拝観が許される。
階段にて楼上に上る。
楼上からの景観
組み物部材が手に出来る感じである。
楼上をひとまわり
真宗本廟の額
『仏説無量寿経』の会座を表わす釈迦(中)・阿難(左)・弥勒(右)の三尊像
須弥壇
天井画
楼上の3面の天井には竹内楢鳳(たけうちせいほう)が[飛天舞楽図]を描くはずであったが果たされず、実物大の原画のみ
が現存する。
参考資料≪真宗本廟東本願寺、国文化財データーベース、他≫
■■■ 真宗本廟東本願寺桜下亭(おうかてい)
明治42年(1909)、前年に引退した第二十二代・現如上人の隠居所として建てられた東京・霞ヶ丘別邸の一部を、昭和14年(1939)
の本山へ移築したもの。
端正な造作の茶室が設えられているほか、座敷には元来、岐阜別院の書院を飾っていた円山応挙筆の稚松(わかまつ)・壮竹(そうちく)
老梅の襖絵がある。
桜下亭茶室 曲木の床柱・書院棚の軽妙なくり抜きなど、簡素な中にも工夫が凝らされている。
桜下亭の廊下には、建造当時のガラス戸がそのまま残っている。
応挙筆「壮竹」図
「松」「竹」「梅」の間が並んでいる。松の間は金箔の下地の上に描かれている。ノータッチのこと!
応挙筆・「老梅」図。桜下亭にある応挙の襖絵は、明治24年(1891)の濃尾大地震で倒壊・焼失した岐阜別院から写したもの
■■■ 真宗本廟東本願寺鐘楼
国登録文化財
建築:明治27年(1894)
構造:木造平屋建、檜皮葺、建築面積29㎡
基準:造形の規範となっているもの
解説:阿弥陀堂前方南寄りの高い切石垣基壇上に建つ。
円柱,三手先,二軒繁垂木で深い軒をつくり,入母屋造,檜皮葺の屋根を架ける。
大梁2本を互いに対角線方向に渡し中央交差部に鐘を吊り,直下に陶製の瓶を埋めるなど特徴をもつ。
大型で総欅造りの質の高い鐘楼。
■■■ 真宗本廟東本願寺造合廊下(つくりあいろうか)
国登録文化財
阿弥陀堂と御影堂を結んでいる廊下である。廊下の両入口に唐破風造門がある。正面が御影堂である。
建築:明治27年頃(1894)
構造:木造平屋建、瓦葺、建築面積110㎡
基準:造形の規範となっているもの
解説:御影堂と阿弥陀堂の間を繋ぐ2筋の廊下のうち東表側にあるもの。
高床,吹放しで,唐破風造,本瓦葺とし,約5,5mの梁間に虹梁を架け輪垂木天井を見せる。
前後に出梁で縁葛を支え擬宝珠高欄を付け,床下にも桁行,梁間に虹梁を架けるなど凝った造りとなる。
真宗本廟東本願寺二筋廊下(ふたすじろうか)
国登録文化財
建築:明治27年頃(1894)
構造:木造2階建、瓦葺、建築面積150㎡
基準:造形の規範となっているもの
解説:御影堂・阿弥陀堂間を繋ぐ廊下のうち裏側にあるもの。
2階建で,階上は棟通りに押入を設けて前後2筋の廊下に分け,階下は中央に通路を取り他は部屋とする。
表側階上は全柱間に異形花頭形の格子窓を明け,背面は全面塗り込めとし,両堂と共通した構えを造る。
参考資料≪国文化財データーベース≫
■■■ 真宗本廟東本願寺大玄関(おおげんかん)
国登録文化財
大玄関は大寝殿と一体として同時期に建てられ、現在も重要な行司の際に正玄関として使用される。
建築:慶応3年(1867)
構造:木造平屋建、瓦葺、建築面積420㎡
基準:造形の規範となっているもの
破風の連続が美しい。 大玄関口
解説:伽藍の北方,大寝殿の北東に接続する。
正面入母屋造,桟瓦葺で,式台を構え,田字型に4室を取り周囲に広い入側縁を回す。
元治元年火災直後の仮建ての建物で装飾要素は少ないが,10mを越える間口の式台など格式の高さを示している。
寺内で現存最古の建物。
大玄関から玄関門、菊の門をみる
■■■ 真宗本廟東本願寺大寝殿(おおしんでん)
国登録文化財
慶応三年(1868)に上棟され、現在の本廟内では一番古い建物である。
4度目の火災となった蛤御門の変後、仮の御影堂となった。
大寝殿は表向諸殿(公式行事・儀式に使用される部分)の中心であり、現在では報恩講のお斎(とき)接待などに
使用される。
建築:明治元頃(1868)
構造:木造平屋建、瓦葺、建築面積945㎡
基準:造形の規範となっているもの
解説:大玄関南西に雁行して接続し,東本願寺正殿として重要な法要儀式の場となる。
入母屋造,桟瓦葺の大きな妻面を正面に見せ,平面は真宗大広間の形式を踏襲する。
座敷の最奥は全面上段とし,床・棚・書院さらに帳台構を備える。幕末真宗大広間の姿をよく伝える。
上段の間の障壁画は竹内楢鳳が昭和9年(1934)に描いた力作。仏教の教えとの出会いがテーマーとして描かれている。
画題は右から「風竹野雀」「歓喜」「古柳眠鷺」。それぞれ現世の闘争・遇法の喜び・浄土の静寂を表わすという。
「雀」が切り取られた。それ以後はガラスでガードされている。反射して写真が取れない。
■■■
■■■ その他の諸堂
総合案内所
参拝接待所
昭和9年(1934)、現在地に在った旧志納所に替えて、武田吾一博士の建築慣習のもと、参拝者の休憩や礼金・志納・寄付などの
受付窓口として新設された。
南から見た参拝所。全国から訪れる門徒を迎える窓口である。
参拝接待所は、御影堂と高廊下で結ばれており、廊下からの境内が見渡せる。
また現建物の北側地下部には、平成10年(1998)の蓮如上人五百回御遠忌の記念事業として、建築家・高松伸氏監修のもと、最新
鋭の視聴覚機能を備えた[真宗本廟視聴覚ホール]が竣工し、併せて仏間や応接室、ギャラリーなどが設けられている。
手水舎
御影殿に向って左側手前に位置する。
百間廊下
一般通路として利用される廊下と門首が使用される廊下。壁を隔てて向かい合って造られている。“うるし”が剥がれている。
宮御殿・白書院・大寝殿、などに行かれる際に門首が使用される廊下。“うるし”が残り、黒光りしている。凝った造りになっている。
資料≪真宗本廟東本願寺、国文化財データーベース、他≫
All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中