





Monthly Web Magazine Apr..2025
■蟇股あちこち 60 中山辰夫
今月は奈良の西大寺と京都御所です。
西大寺は東大寺と共に大伽藍を有する大寺でしたが、何度もの火災で焼失し、現在の建物は江戸期代のものです。大茶盛で有名です。
京都御所、築地塀の東西南北に六つの門があります。それぞれの門には蟇股の彫刻が程化され、華やかな、格調ある門に一役買っています。
奈良市西大寺柴町1-1-5
西大寺は市街地の中にあり、駅の南出口から南に3分も歩けば東門に着きます。
奈良時代、東の東大寺に対して西の西大寺と称されて、南都七大寺の一つに数えられる程の官寺でした。
天平宝字8年(764)、称徳天皇(聖武天皇と光明皇后の娘)の四天王像造立の発願で起工、四天王像の完成とともに伽藍が開かれました。
伽藍は薬師金堂、東西両塔、四王堂院、十一面堂院、など百十数の堂舎が建ち並び、まさしく東大寺に対する西の太寺に相応しいものだったとされます。
平安時代は再三の火災で衰微の一途をたどり、室町時代は兵火で堂塔を失いましたが、現在の建物は江戸時代に再建されました。
アプローチ
境内は広く諸堂も建ち落ち着いた雰囲気の中に歴史を感じさせる境内です。
各堂内には国重要文化財の仏像が安置され、国重文の絵画・工芸品・古文書が多く残っており、往古の盛時を語っています。
■東門





■四王堂 再建 :1674年 唯一創建時の由緒を伝えます


■護摩堂 奈良市指定 建立:1624年 桁行三間 梁間三間 寄棟造 背面軒下張出付



■本堂 国重文 建立:1799年 桁行七間 梁間五間 一重 寄棟造 正面向拝三間 本瓦葺
総板壁 装飾性の少ない伝統的な様式 江戸時代後期の大規模仏堂建築の代表作とされます





□三間向拝の蟇股と木鼻






□身舎廻りの蟇股





![]()
![]()
![]()
■愛染堂 県指定 移築:1762年 京都近衛家の政所御殿 南北十一間 東西八間 宸殿造の仏堂 本瓦葺




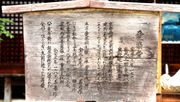
■鐘楼 奈良市指定 建立:1661~73年 移築:幕末 摂津多田院より 桁行三間 梁間二間 袴腰 入母屋造 本瓦葺



![]()
□蟇股は4面に配されています










■東塔跡基壇


京都市上京区京都御苑
現在の京都御所は1331年から1869年の間、天皇が住み、儀式や催しを執り行った場所です。
長い年月の間に皇居の焼失や災害、方違いなどから、かなりの変遷を経ました。
織田信長が修理し、豊臣秀吉が1590年に内裡を新造、徳川家康も1613年に造営を行い、光秀の時代に修理・拡大・整備が進みました。
その後も火災での炎上が重なりました。現在の御所は、1855年に完成したものです。広さ27万7千坪、周囲は石垣を積んだ九つの門に囲まれています。





御所の周りは東西約250m、南北約450mの築地塀が廻らされ、東西南北に六つの門、十三の穴門が外とつながっています。



築地塀は五筋の白線を付けた薄い泥色の壁で、格調ある清閑な雰囲気をもち、約11万3千㎡の中に十余の木造宮殿群を囲んでいます。
乾御門から入り、進めて行きます。
■皇后門 本瓦葺 棟門様式 本柱の前後に支柱はありません。破風にはなやかな彫刻が見られません。
京都御所の西側の北に建立。皇后の通用門。屋根は本瓦葺です。築地の瓦には菊の紋章が焼き込まれています。




■清所門 瓦葺
かっては御台所御門と呼ばれ御所の勝手口として使用されていました。御所の参観時はこの門から入ります。





■宣秋門(きしゅうもん) 四脚門 切妻造 檜皮葺 笈形は中央に大瓶束と呼ぶ円柱が建っています、
□外側






蟇股
蟇股は杖を持った仙人や瓢箪から駒ですが、琴高仙人などほかにもあります。




□内側



蟇股




宣秋門は別名「唐門」とも(公卿門)とも言われます。
従来は門外で乗り物を降り、徒歩で出入りしましたが、天皇より「牛車宣旨、手車宣旨」を賜ったことから車の儘通行ができ、車寄せが設けられました。
□御車寄



□新御車寄



■建礼門 建立:1855年 切妻造 檜皮葺 平入 四脚門 1613年から今の位置にあります。京都御所の南面正面 カシの木
□外側
南正面に建つ、最も格式の高い門とされます。五月の葵祭、十月の時代祭の行列が建礼門の前からスタートします。扉は透かし彫りの花狭間です。
円柱の本柱と前後に二本の角柱の支柱、計四本が立つ四脚門です。



蟇股 二重虹梁蟇股 中央・浪に龍
蟇股は正面に菊に唐草、背面は雲龍 冠木には仙人や花鳥が彫られています。






□内側




蟇股 仙人と神龜、 亀乗り仙人、仙人と虎





■建春門 四脚門 平入屋根 向唐破風 高さ11.45m 向唐破風をもった唐門の一種。
□外側
天皇が建礼門から入られるに対し、皇后の出入りに開かれた門です。かっては「日御門」と呼ばれました。



蟇股
蟇股は唐松、羊、仙人の彫刻があって、皇后の門らしくきりりとした格調が感じられます。




-s.jpg)


![]()
![]()
□内側




蟇股



■猿ケ辻
御所の東北の角で鬼門に当たるため、塀の角が取られています。
猿神像:築地屋根には、鬼が去るようにと御幣を担いだ猿神像が安置されています。





■朔平門 三間一戸 四脚門 桧皮葺
南側の建礼門に対応して北側に建っています。「朔)は「北」の意味です。




□蟇股 牡丹に獅子、鳳凰など






■参内殿玄関



参考 京都御所のブログに詳細な内容の案内があります。
All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中